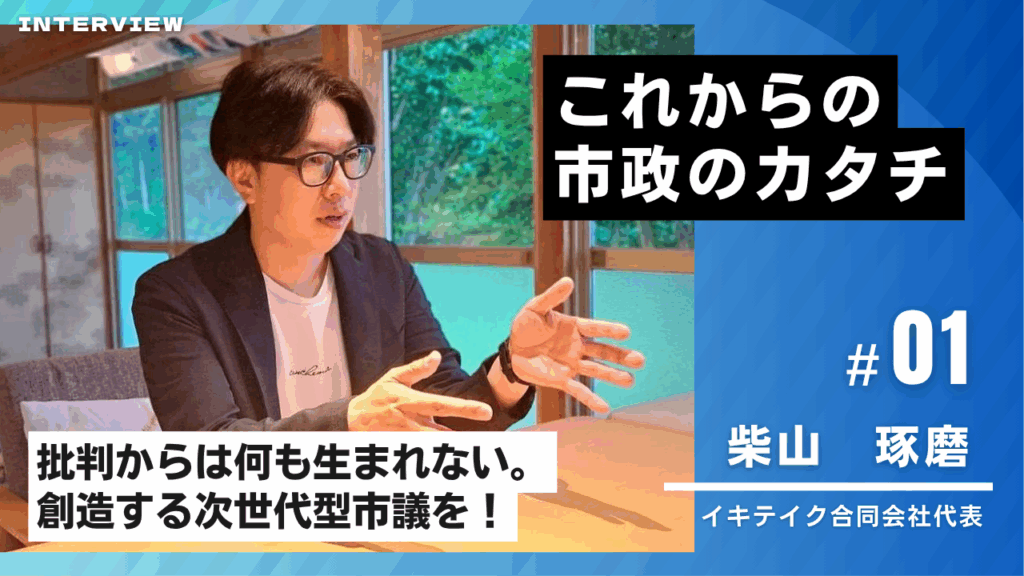壱岐市議選(2021年)において、完全単独で選挙運動を展開し、独自のスタンスを貫いた柴山琢磨さん。
「壱岐市みんなの政治」の発起人でもある柴山さんの当時の挑戦から、現在の活動、そして壱岐市の未来に向けて思うことをインタビュー形式で伺いました。
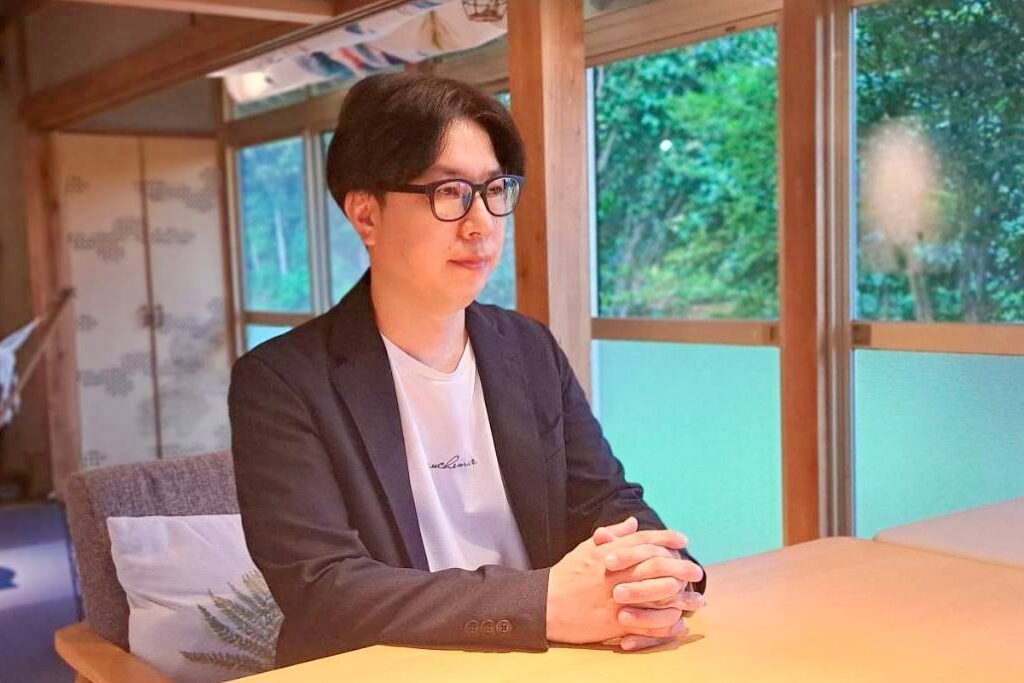
――2021年の壱岐市議選では、異例の「一人選挙運動」を行ったそうですね。
はい。人生初の選挙でしたが、これまでの「地縁・血縁選挙」を打破したくて、すべて自分一人で行いました。おそらく全国的にも珍しいケースだと思います。
選挙前の選挙公報、SNS発信、チラシのデザイン、印刷、事務処理、選挙期間中の選挙カーやウグイス嬢も全部ひとりです。唯一、告示日のポスター掲示だけは家族と親戚にお願いしましたね。
「そんなやり方もあるんだね」と、好意的な反応も多くいただきましたが、真夏の選挙だったこともあり、体力的にはかなり過酷でした。毎日、選挙運動が終わると倒れ込むように休み、翌朝はまた気力を振り絞って起き上がる――そんな一週間でした。
支援団体を一切持たないからこそ、どんな人にも利害関係なく、公正で中立な市議であることを目指しました。
でも、結果は455票で落選。
ギリギリまで悩んでの立候補というタイミングの遅さも要因かなと思いましたが、やはり、悔しさはありましたね。
短い期間の中で、455票の支援をしてくださった皆様に改めて感謝しています。
――前職は壱岐市役所の職員でしたが、行政経験を活かせたのでは?
市役所では壱岐市CATV事業を担当したり、都市部のベンチャー企業との協業等でメディア出演も多く、幅広い経験と実績を積んできました。
退職後も、郷ノ浦町の花火大会の復活や著名人を誘致しての講演会、コロナ禍の時は飲食店支援プロジェクトやオンライン成人式を行ったりと、地域に新しい風を吹き込む活動を続けてきたつもりです。
でも、「元市役所職員」というイメージが「変化を起こす人」として、受け取られなかったのかもしれません。
選挙期間中はSNSでの発信にも力を入れましたが、一部からは心ない誹謗中傷もありました。選挙後には、そのストレス等から数ヶ月、心身のバランスを崩してしまったんです。
まさに、「出る杭は打たれる」を実感しましたね。

――現在はどんな活動をされていますか?
2019年に立ち上げた「イキテイク合同会社」の代表として、WEBデザインやITサポートなど、パソコン関係の“何でも屋さん”として活動しています。
壱岐市農協のロゴデザインを手がけたり、最近ではAIを使った作曲にも取り組んでいます。自分が制作に関わったプロダクトが、壱岐島のあちこちに存在しているのは、とても楽しく、やりがいを感じる瞬間です。
また、2022年には壱岐初の動物保護団体「壱岐島わんにゃんお守り隊299」の発起人として、団体の立ち上げや運営にも携わりました。
さらに、今年春のセンバツ甲子園に出場した壱岐高校野球部後援会では、クラウドファンディングやSNSでの情報発信を担当し、クラファンでは約500万円、SNS動画は累計200万回以上の再生を達成しました。
最近では、長崎県のメディア安全指導員として石田中学校を訪れ、中学生向けにSNSの使い方について講演も行いました。生徒たちの反応がとても良く、これからの活動への手応えを感じています。
ただ、人口減少が進む壱岐の将来に不安を感じたこと、そして自分自身の気分転換も兼ねて、2023年からは福岡でも営業を開始し、今は壱岐と福岡の2拠点生活をしています。壱岐と福岡の両方で子ども向けプログラミング教室もやっています。
現在は、自分の仕事をしながら、2024年からは障害者支援のための「デジリハ」というデジタルリハビリテーションツールを開発する企業で、九州・沖縄エリアマネージャーを務めています。
西日本各地の障害福祉施設を訪れ、リハビリを必要とする子どもや大人、高齢者と向き合う毎日です。
北九州市や福岡市などの自治体とも連携しながら、障害福祉の分野でイノベーションを起こすプロジェクトも進行中です。
さらに、2025年からはAI英語タイピングツール「TypeGO」の営業にも携わっており、自治体との実証実験を通じて、子どもたちの英語力向上や英語教員の業務負担軽減、さらには観光事業者のインバウンド対応支援などにも取り組んでいます。

※デザインや写真・動画等のクリエイターの仕事から、業務委託のマネジメント、島のパソコン屋さんの仕事を黙々と行う柴山さん
実は、これらの仕事はどちらも、市役所時代のご縁から生まれたものなんです。これまで自分が関わったことのなかった分野ではありますが、とても興味深く、毎日が新鮮な学びの連続です。
また、前職が公務員ということもあって、行政の方々とお話しする際には、とても重宝がられています。行政の言葉遣いや仕事の進め方って、一般企業の方にはなかなか伝わりにくい部分が多いんですよね。
たとえば、意思決定の順序や時間のかけ方、予算の仕組みなど。そうした“官”の文脈を理解しながら、“民”のスピード感や実行力と調整する――いわばパイプ役として、企業側からも行政側からも喜ばれています。
特に行政の方からは、「元公務員」と伝えるだけで、安心されることが多いです。どこか“仲間意識”のようなものを持っていただけるんでしょうね。そういう信頼関係があるからこそ、双方の橋渡しとして自分の役割を実感できています。
――とても多彩な活動ですね。ご自身の働き方にこだわりはありますか?
そうですね、自分の本業だけでもかなりの業務量なんですが、現在の2社以外に、実はもう1社、大手の企業からもオファーをいただいていまして、、(笑)。
今は正直、ほぼ365日仕事をしているような状態で、今回の市議選の話が出るたびに「次は頑張って!また出るよね?」と声をかけていただいたのですが、とてもじゃないけど今はその余裕はありませんでした。それに、市議にならなくても、これまでどおり社会へのアクションは起こせますしね。
今は何より、身近で自分を必要としてくれる人たちのために力を尽くしたい、日本や世界でイノベーションを起こそうとしている人と働きたい、そんな想いで働いています。
今の自分のテーマは「多拠点居住×多業多福」です。
一つの場所や職業に縛られず、自分のスキルを活かせるフィールドで、社会に貢献していく。
そんな生き方・働き方を大切にしています。

――今、壱岐市の市政や市議に対して、どんなことを求めますか?
これまでの市議には、「行政を監視する役割」が強く求められてきました。でも、これからの時代は、それだけでは不十分だと思っています。
行政とともに政策を創り上げていく、「創造型」の市議が必要と考えています。ネガティブな批判だけでは、何も生まれません。
より良い社会を実現するには、具体的な知恵や提案、そしてそれを実行に移す力が不可欠です。
そしてそれを、市民とともに進めていける議員であってほしいと思います。
一方で、市政にも大きな課題があります。
今、私は全国の自治体職員とお話させていただく機会が多いのですが、その中で強く感じるのは、壱岐市役所の職員は、本土の他自治体と比べてると情報量や経験値、フットワークに差があると感じることです。
離島という環境に守られすぎていて、外との交流が少ないことも要因の一つだと思います。現在は慶應義塾大学との連携研修なども行われていますが、対象はごく一部の職員に限られているのが現状です。
私は、壱岐市の未来を変える力を持っているのは市長ではなく、職員、そして市民一人ひとりだと考えています。
AIなどのテクノロジーを活用して業務を効率化し、そこで生まれた余白を「学び」や「自己研鑽」にあてることで、職員の成長を後押しすることができます。
そして市民もまた、自治体任せにするのではなく、自分たちの地域をどう良くしていくかを考え、行動する主体になってほしい。
行政と市民がともに学び、ともに挑戦することで、壱岐の未来はきっともっと明るくなるはずです。
その一つとして、この「壱岐市みんなの政治」というプラットフォームを作っています。

――議員定数削減や議会改革については、どうお考えですか?
よく「定数を削減すると議員のなり手がいなくなる」「市民の声が届かなくなる」といった声を耳にしますが、それは正直、保身にすぎないと思います。
今はSNSやインターネットの普及で、情報収集も意見の吸い上げも、以前に比べてずっと容易になっています。
言い訳は、もはや通用しない時代です。
壱岐市の将来はけして明るくありません。その現実をしっかりと直視することが必要です。
市議会も行政も、まず「身を削る」覚悟が必要です。
その一つの具体策として、私は議員報酬を「月額制+日当制」のハイブリッド型にすべきだと考えています。
たとえば、最低限の生活を支える月額基本報酬に加え、出席日数や議会活動に応じて支払われる活動手当という形です。
これは、真面目に取り組む議員には正当に報いる一方、出席率や活動実績の低い議員には自然と報酬を抑える、メリハリのある仕組みになります。
議員という立場を「給与のもらえるボランティア」のように捉えるのではなく、市民の意思をくみ取り、行政を動かす責任ある役割として、もっと強い責任感と行動力を持つべきです。
そして何より、市議を「就職先」にしてはいけない。
きちんと自ら社会活動や経済活動ができ、民間や地域社会とつながっている人だからこそ、現場の声や課題がリアルに見えてくる。
そういう人が議会に入り、現実に根ざした提案をしていくべきだと考えています。
――最後に、市民に向けて伝えたいことは?
市議会議員は選ばれた市民の代表ですから、主権者である市民が頭を下げる必要はありません。むしろ、市議を「使い倒す」くらいの気持ちで臨んでほしいと思ってます。
僕が市議ならどんどん市民のみなさんに使ってもらいますね。コスパ良くめちゃくちゃいい仕事できるとは思います。
壱岐市の未来を良くしたい。その想いに正直に、全力で取り組んで結果を出せる人材こそ、これからの壱岐には必要です。

柴山さんの言葉には、批判ではなく、未来への具体的な提案と覚悟が詰まっていました。
壱岐の未来を形づくるのは「誰か」ではなく、「わたしたち」なのだと。
編集部ではこれからも壱岐市内で活動・活躍する人へのインタビューを行い、市政や想いについて語っていただく予定です。
ご興味のある方は、お問い合わせフォームから編集部にご連絡ください。