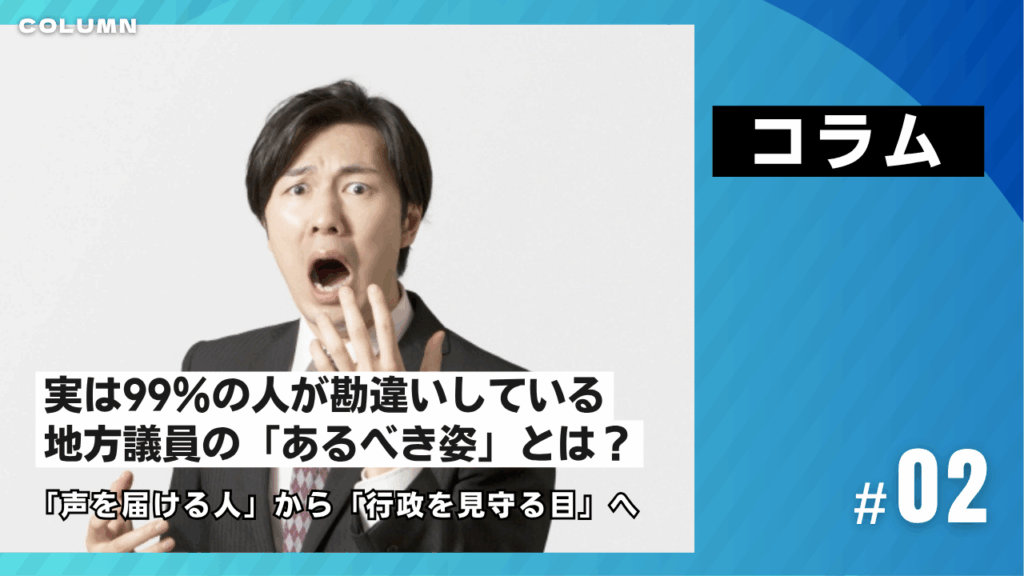選挙の時期になると、耳にするフレーズがあります。
「あなたの声を議会に届けます!」
一見もっともらしく聞こえるこの言葉。
「地方議員の仕事は市民の声を拾って行政に届けること」――そう思っている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、地域の課題に耳を傾ける姿勢は必要です。
しかし、本来の議員の役割は「声を届ける」ことそのものではありません。
この記事では、地方議員に本当に求められている役割と、今の時代に即した「あるべき姿」について整理します。
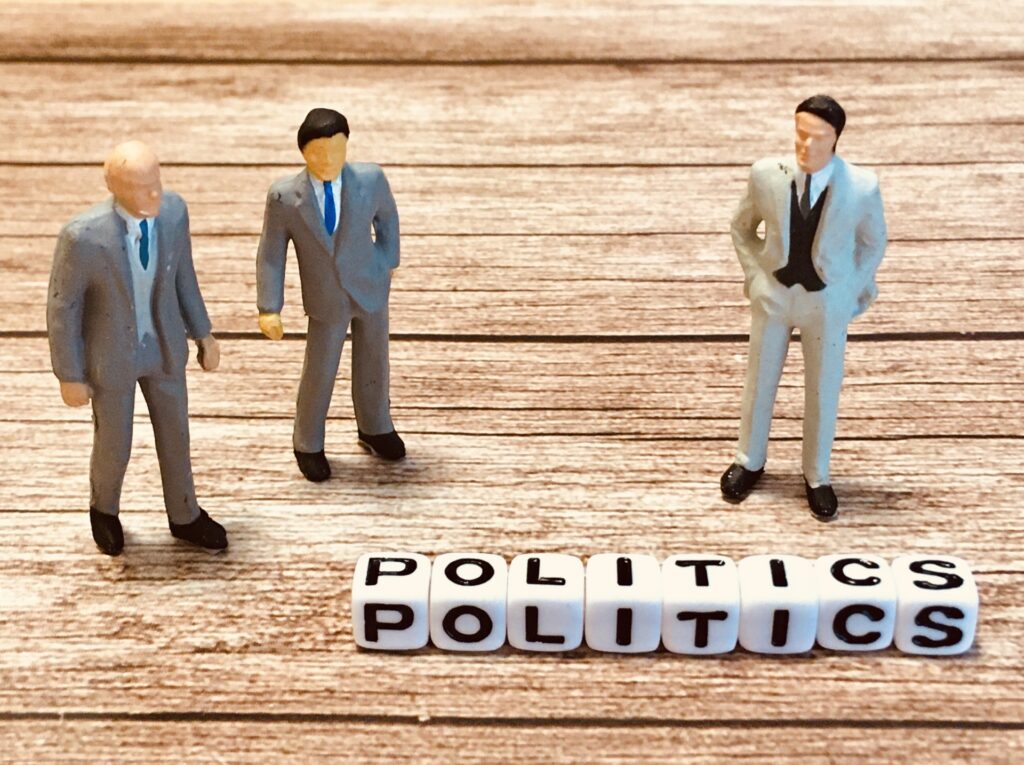
■議員の本質は「行政のチェック機関」
地方議会は、住民に選ばれた議員によって構成される、意思決定と行政監視の場です。その中で議員には以下のような役割があります。
- 予算や条例の審議・議決
- 行政施策の妥当性の検証
- 決算の認定や監査請求
こうした活動を通じて、行政が適切に職務を遂行しているかどうかをチェックする責任を負っているのです。
つまり議員は、単に「声を伝える」人ではなく、行政の仕事を監視し、必要があれば是正を求める存在。予算の使い方や政策の方向性に対して、法的根拠と責任をもって判断する立場なのです。
■「声を届ける」という誤解の構造
「議員が市民の声を拾って行政に届ける」というイメージは、根強く社会に浸透しています。しかし、これは本来の構造からは外れています。
本来、住民の声には行政自身が直接耳を傾け、政策に反映する仕組みを整えることが前提です。
議員が「伝書鳩」のような役割に終始してしまうと、行政の意思決定の妥当性を判断するという本来の職責がぼやけてしまいます。
■法律が示す議員の役割とは?
地方議会の役割は、法律で明確に定められています。
地方自治法 第96条(議決事件)
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例の制定、改廃
二 予算
三 決算の認定
このように、地方議会は行政の政策判断や財政運営を審査・決定する機関と位置づけられています。これは、議会が行政のチェック機関であることを法的に保障しているということです。
一方で、「住民の声を聴くこと」については法的義務としては書かれておらず、多くの場合は議会基本条例などで努力義務として定められているにすぎません。

■「議員を通さないと行政が動かない」は本末転倒
次のような事例、あなたも聞いたことがあるかもしれません。
「市民が市役所に相談したけれど相手にされなかった。議員に頼んで話を通したら、急に対応が良くなった。」
いわゆる「市役所あるある」ですが、これは本来あってはならないことです。
公務員の基本は公平・公正な対応です。「誰から言われたか」で仕事の質が変わるのは、プロの公務員とはいえません。
この構造こそが、「議員は声を届ける人」という誤った印象を生んでいるのではないでしょうか。
■本来の議員の仕事は「決める」こと
地方議会は、ただ意見交換をする場ではありません。条例を制定し、予算を審議し、地域の未来を方向づける――重い意思決定の場です。
そのため、議員には以下のような資質が求められます。
・行政に対して是々非々の姿勢で向き合う独立性
・長期的な視点での政策評価力
・市民全体の利益を見据える公平性と柔軟性
・説明責任を果たす情報発信力
■若返りと多様化が求められる理由
現在、多くの地方議会では高齢化が進み、若者や女性の参画が極めて少ないのが現状です。これは、多様な声を政策に反映するうえで大きな障壁になっています。
一方で、SNSやオンラインツールを使えば、若年層やマイノリティの声も以前より可視化しやすくなっています。
今必要なのは、議員数の多寡の議論ではなく、
「誰が議員になるのか」、「どのように活動するのか」
という“議会の質”の改革です。
■結論:議員の本来の使命とは何か?
地方議員の本質的な姿とは、「声を拾う人」ではなく、「行政の判断を見守り、責任ある決定を下す人」です。
議員は、行政に対して適切な距離を保ちながら、地域全体の未来を見据えた判断者・監視者でなければなりません。
また、説明責任を果たし、議会活動を可視化することで、住民に信頼される議会をつくることも、その責任の一部です。
「誰のために、何のために、どう議論するのか?」
この問いを今こそ、議員も有権者も、自らに問い直す時です。
「議会とは何か。議員とは誰の代表で、何をする人なのか。」
この基本に立ち返ることが、これから本当に必要な地方自治や地方創生の礎となるでしょう。